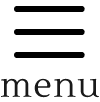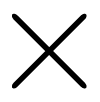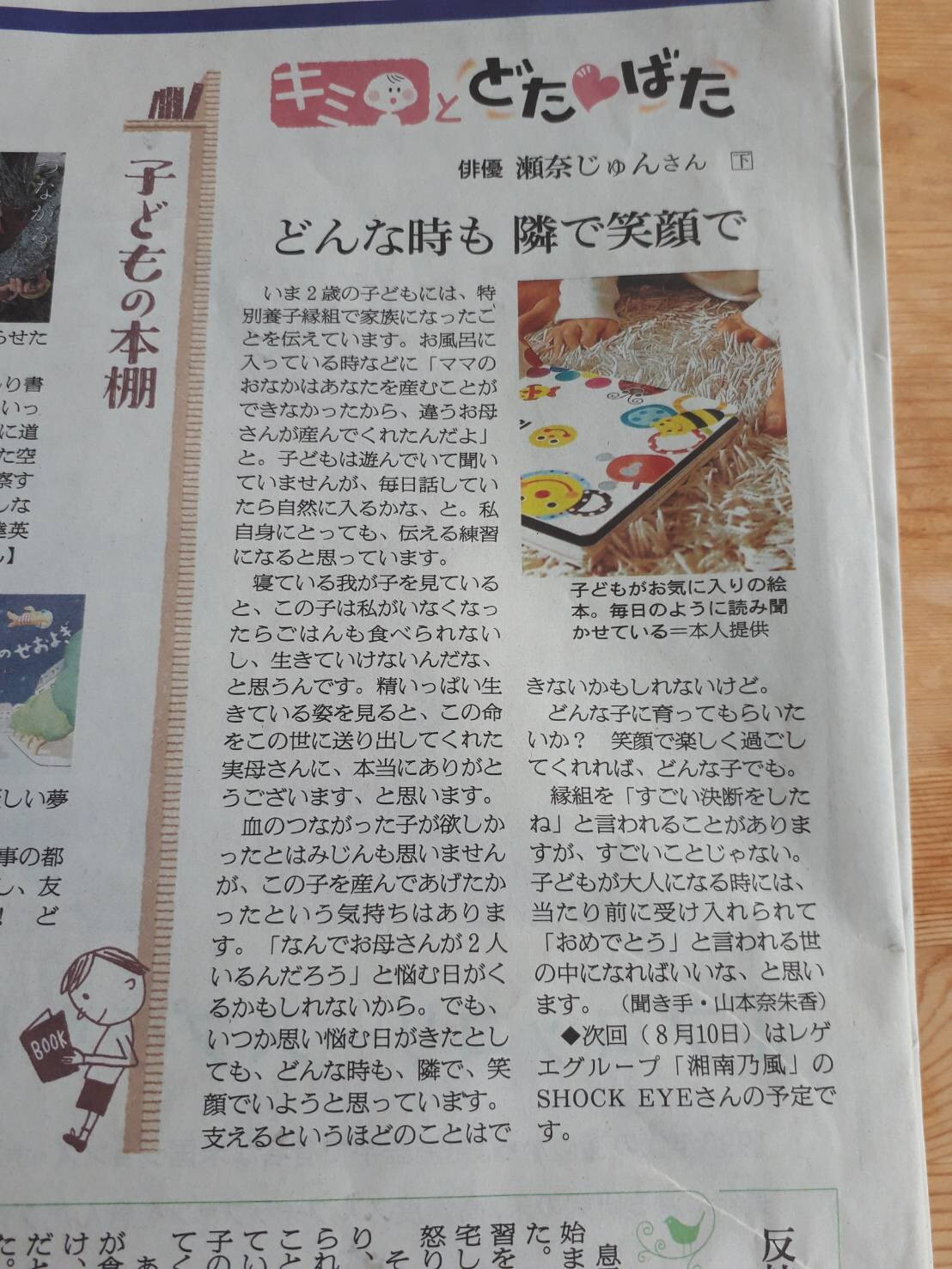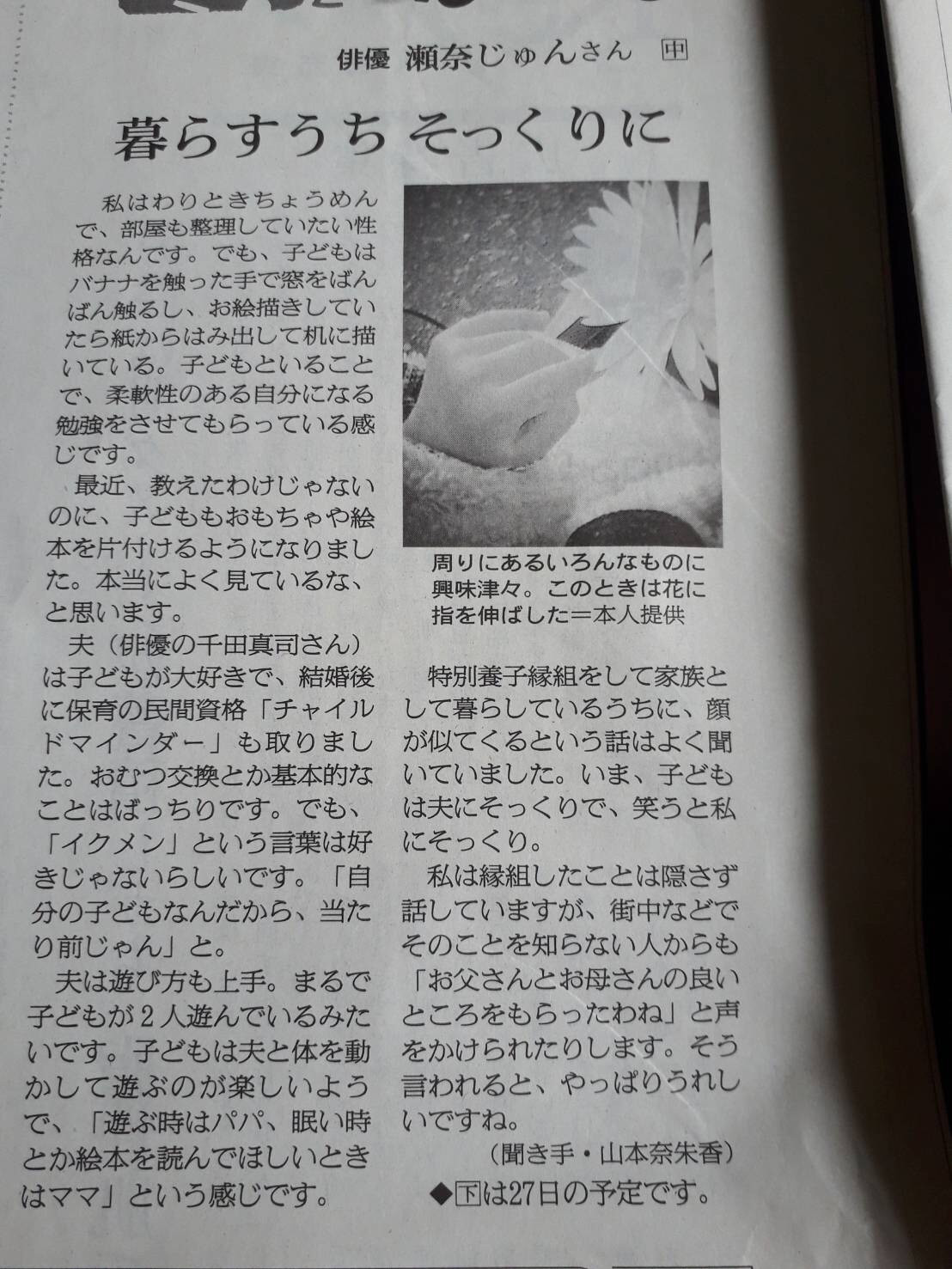インフォメーション
- 2024-03(1)
- 2023-06(1)
- 2023-05(1)
- 2023-02(1)
- 2022-12(3)
- 2022-06(1)
- 2022-05(1)
- 2022-04(1)
- 2022-01(1)
- 2021-04(1)
- 2021-03(1)
- 2021-02(1)
- 2021-01(1)
- 2020-10(2)
- 2020-09(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(5)
- 2020-04(1)
- 2020-02(1)
- 2020-01(4)
- 2019-12(2)
- 2019-11(1)
- 2019-10(4)
- 2019-09(5)
- 2019-08(4)
- 2019-07(1)
- 2019-05(2)
- 2019-04(3)
- 2019-03(3)
- 2019-02(3)
- 2019-01(5)
- 2018-12(1)
- 2018-11(1)
- 2018-10(1)
- 2018-09(1)
- 2018-08(1)
- 2018-07(4)
- 2018-04(2)
- 2018-03(2)
2019/09/07
[ブログ]ドキュメンタリー映画 隣る人
ドキュメンタリー映画
2019/09/07
[ブログ]小さき命のために
小さき命のために 一産婦人科医の罪と栄光の軌跡
出雲井 晶
先日、「愛知方式」で知られる矢満田さんと、「こうのとりのゆりかご」を創設した蓮田先生にお会いする機会があり、お二人が成してきた偉業とお二人のお人柄に触れることができ、私が密かに抱いていた望みが成就した。
実はもう一人、出来ることならお会いしたいのだが、もうお会いすることの叶わない方がいる。
菊田昇さん
1973年菊田医師赤ちゃん斡旋事件として世間を巻き込んで問題提起をした菊田昇医師。
産婦人科医として人工妊娠中絶手術を行う中で葛藤し、悩んだ末に法を犯して100人以上の赤ちゃんを無報酬で斡旋した菊田医師。
当時、妊娠28週までは人工妊娠中絶手術が認められていたが自身の経験から妊娠7ヶ月の胎児は生きて生まれてくるとして妊娠7ヶ月以降の母親を説得し出産してもらい、養親が生んだように偽りの証明書を作成し、実子として託すのである。
特別養子縁組のまだない時代に、生みの親と、その子どもと養親を救う最善の手段として10年の間、法を犯し続けた。
73年、「男の子の養親を求む」というチラシを見つけた毎日新聞の記者が菊田医師を取材したことが、きっかけとなり全国的に知られる「赤ちゃん斡旋事件」となった。
が、これも菊田医師の目論見の内であった。
現行の養子縁組では子棄て、子殺し、中絶は一向になくならない。(昭和54年度の中絶件数は厚生省の統計で約61万、実数は約200万とも言われていた。)
世間を巻き込んで問題提起をし「完全養子縁組」の制度を実現しなければならないと菊田医師は考えていた。
菊田医師は産婦人科医になる前、キリスト教徒だった。
産婦人科医になること、それは人工妊娠中絶を行うということだ。その行為を主であるイエス・キリストに見られることに耐えられず、聖書を捨てたという。
このことから、菊田医師が心の奥では中絶手術を受け入れられていなかったことが想像できる。
法的には妊娠28週までの中絶手術が認められていたが、妊娠7ヶ月と診断し、中絶手術を行ったある時にまさかの出来事が起きた。
母体から引っ張り出した赤ん坊が泣いたのだ。
菊田医師も初めての経験だったらしく、戸惑い悩んだ末にその子を生まれたままの姿で置き去りにした。
母親は中絶を望んでいる。育てられない。誰にも知られず、堕ろすことが出来ればいいと考えているのだから、その子を助ける術がなかったのだろう。
翌朝、その子は亡くなっていた。とても冷えた夜だったらしい。
この経験は後の菊田医師にとって、とてつもなく重い十字架となり、原動力にもなった。
そして菊田医師は覚悟を決めた。
それから10年余り、100人以上の子どもを法を犯しながら、無報酬で斡旋し続けた。
初めて、菊田医師のこの善意の犯罪が毎日新聞の一面で取り上げられた1973年から特別養子法が施行される1988年まで、実に15年の歳月を要した。
こうして、ひとりの人間が自らの人生を投げうち世論を巻き込んで長い年月をかけて施行された特別養子法。
今私が、我が子を抱いているのも、菊田医師を始めとした多くの先人のお陰なのだと心から感謝している。
その後、菊田医師の一連の活動は世界で認められ、国連の国際生命尊重会議(東京大会)で第2回の「世界生命賞」を受賞した(第1回オスロ大会ではマザー・テレサが受賞)。その4か月後の1991年8月癌により死去された。
当時7歳だった自分が、26年後に、菊田医師の影響を多大に受けた特別養子縁組によって父になるとは、当たり前だが思ってもおらず。
今の自分がこうして振り返る事によって、当時の自分と、想像の中の菊田医師との間に、極々細い、でも確かな縁を感じられるような気がしてきます。
そう感じたいだけですが。。。
こんな風に、今の自分の活動が、いつ、どのように、誰の人生に影響を与えるのか。
1人でも多くの子どもが笑顔になれたらと願っています。
&family..
千田真司
2019/09/03
[ブログ]andfamily repo vol.7