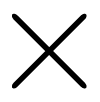インフォメーション
- 2024-03(1)
- 2023-06(1)
- 2023-05(1)
- 2023-02(1)
- 2022-12(3)
- 2022-06(1)
- 2022-05(1)
- 2022-04(1)
- 2022-01(1)
- 2021-04(1)
- 2021-03(1)
- 2021-02(1)
- 2021-01(1)
- 2020-10(2)
- 2020-09(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(5)
- 2020-04(1)
- 2020-02(1)
- 2020-01(4)
- 2019-12(2)
- 2019-11(1)
- 2019-10(4)
- 2019-09(5)
- 2019-08(4)
- 2019-07(1)
- 2019-05(2)
- 2019-04(3)
- 2019-03(3)
- 2019-02(3)
- 2019-01(5)
- 2018-12(1)
- 2018-11(1)
- 2018-10(1)
- 2018-09(1)
- 2018-08(1)
- 2018-07(4)
- 2018-04(2)
- 2018-03(2)
2019/01/22
[ブログ]andfamily repo vol.3
[and family repo vol.3]
取材協力者:金森三枝氏
東洋英和女学院大学人文学部人間科学科卒業。
東洋英和女学院大学大学院修士課程人間科学研究科修了 (人間科学修士)。
東洋英和女学院大学人間科学部人間福祉学科助手、専任講師を経て、現在東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科准教授。「家庭支援論」「保育相談支援」「病児・病棟保育論」「保育実習」などの科目を担当。
神奈川県子ども・子育て会議委員。
今回は児童福祉に長年関わり、自身が様々な病院で行ってきた「遊びのボランティア」の活動を通して病気の子どもたちとその親、きょうだいの支援を続ける金森氏にお話を伺う機会を頂いた。
これまで&family..として養親さん、養子さんご本人のインタビューを通して特別養子縁組の背景を垣間見てきたが、今回はまた違った角度から特別養子縁組の意義を見出せていけたらと思っている。
[医療と保育]
医療の現場に保育は必要なのか。
就学している子どもの為の院内学級や、病棟内に設置されているプレイルームなどは、なんとなく耳馴染みがあるのではないだろうか。
病院=医療。
この図式に疑問を持つ方は、いないだろう。
では、病院=保育。となると、どうだろうか。
病院はあくまで医療の専門の場所で、そこでは治療が最優先であり、狭い個室、もしくは大部屋で決められた時間に食事、検査、薬を飲み、退屈に過ごす場所。さらに重い病気の場合は外に出ることも制限され、苦痛の伴う処置に、面会の自由までも奪われる。
この状況を仕方ないと受け入れるしかないのだろうか。
病気の子どもや家族への支援にあたってきた金森氏の回答はこうだ。
入院児のQOL(Quality Of Life=生活の質)を向上させることも、子どもの権利保護の観点からとても重要なことだということ。
治療や入院している子どもたちも、最善の利益を得る権利を有する。
そしてその為に、病棟や医療の場で働く保育士など専門の職業があり「遊びのボランティア」も必要とされているということなのだ。
「遊びのボランティア」では実に多角的な支援が行われている。
一つ目に、前述した通り、病児のQOLを向上させる為の支援。
様々なことを見聞きし、体験し、日々成長していく年齢の子どもが、治療のためとはいえ、極端に制限を強いられた環境で過ごすことが望ましいとは誰も考えないだろう。
もちろん生死に関わる瞬間を除いての話だが、できる限り日常に近い形で、遊び、笑っていられる環境が子どもには必要なのだ。
その日常が、著しく損なわれるとパニックを起こす子どももいる。
同時に、どうしても閉鎖的になってしまう院内での生活で積極的に社会との繋がりを持てるようにしていくことも大事な支援の一つである。
例えば、通っている幼稚園、保育園、小中学校との関わり、地域の行事などがある。
二つ目に、親への支援。
愛する我が子の看病とはいえ、長期間続く場合、親への負担も相当なものだ。
「付き添い看護」となればなおさら、自分の時間というものは皆無に等しくなっていく。
私自身、子どもが5日間の入院をした時に実際に「付き添い看護」を体験した。
私は1泊だったのだが、狭い個室で病気の我が子と二人、感染の恐れがあるからと廊下に出ることもできず、それはそれは息の詰まるような思いだった。子どもも同様に病室での限られた遊びに不満をあらわにし、機嫌が悪くなる。夜は狭いベット(転落防止柵があるため余計に窮屈)に二人で横になる。全く自分の時間はなく、3泊してくれた妻を凄い!よく乗り切ってくれた!と拍手を送りたくなるほどだった。
たかだか4泊5日の「付き添い看護」で十分というほど大変さを身に染みて感じた。
だが、深夜の病院で大部屋に入院する同じくらいの年齢の子どもたちが泣いている声を聞いてしまっては、付き添わずにはいられなくなるだろう。
とはいえ、家庭の事情は様々で、付き添える家庭もあれば、共働きの場合、仕事の都合で付き添えない家庭もある。
子どもの病気、特に大きな病気ともなれば家庭のあり方を揺るがす大きな出来事になってしまうことも少なくはないだろう。
親といえども一人の人間である。そんな「親」に対して、ボランティアが子どもと遊んでいる間のたとえ短い時間でも、子どもから離れ、自分の時間が持てるようにすることは、何よりの支援ではないか。
そして、余命宣告を受けた親からの相談や、子どもが天国へと旅立った後のケアまで、その支援は続いていく。
金森氏は、子どもが元気なときから関わっている人間が一貫して支援を行うことも重要ではないかと話してくれた。
最後は、病児の兄弟姉妹への支援。
重い病や障がいを持つ兄弟姉妹は多くの場合、家庭の中心に病児がいることによって、我慢しなければいけない場面が多くなったり、寂しい思いも口に出せなかったり、自分が注目されない事で自己肯定感が低くなることがあるという。
こういった病児の兄弟姉妹に対して目を向けて支援をしていくことも欠かせないという。
個々の家庭がそれぞれの生活に主体性をもち、入院児、親、きょうだいの関係が相互に尊重されるよう配慮しながら支援をしていくことが重要なのだが、病院における病気の子どもや家族に対する医療以外の側面からの支援の不足、保育士の配置やその人数の少なさ、病院内外の他専門職や他機関、他団体との連携の難しさなどから実践できないという現実的な問題をまだまだ抱えていると、金森氏は話す。
[遊びのボランティア]
金森氏がこれまで23年間の活動のなかで関わった子どもは延べ5000人を超えるという。
その中には、癌のお子さんや身体中の筋力が萎縮してしまう筋萎縮症、心臓病、脳の病気、目が見えない、耳が聞こえない、話すことができないなど重度の重複障害をもったお子さんなど病状や抱える問題は様々だが、一様に重い病のお子さんばかりだ。
幼稚園に通っている頃に出会い、がんの再発を10回以上繰り返して高校を卒業して天国に旅立ったお子さんもいたという。
別れも少なくない活動の中、喜ばしい御縁もあるという。
小学校5年生で出会ったユーイング肉腫という病気と闘っていた男の子は闘病の末に完治し、現在若年性がん患者の為の当事者団体を立ち上げ、活動している。
金森氏の大学の講義にてゲストとして登壇し、未来の保育者を前に自分の経験談を話してくれたという。
こういった出来事が、金森氏にとってどれだけ励みになり、勇気を与えてくれたことだろうか。
私には想像もつかない程であることは間違い無いと思う。
病棟で、子どもたちと話す会話は決して特別なものではない。
普段の何気ない会話から、好きな人ができたなどの相談まで、子どもたちにとって、親でも医療関係者でもない大人との他愛もないおしゃべりが日常を取り戻す数少ない機会なのかもしれない。
2ヶ月ぶりに笑顔を見せた6歳の男の子、いつもは嫌がるお薬を遊びに行きたいからと頑張って飲んだ2歳の女の子、プレイルームに咲いた12人の子どもたちの笑い声、お医者さんごっこを通じて自分の治療と向き合っていく7歳の男の子。
入院している子どもにとっての遊びは、子どもの発育、発達を促すだけでなく、子どもらしい時間を取り戻し、気分転換、ストレス発散、治療への理解、子どもの状態の把握、仲間同士の支え合い、主体性の発揮など様々な意味をもち、病気の子どもの健康な部分や子どもが本来持っている力を引き出すことが可能だと金森氏は語る。
辛い別れも少なくないこの活動を、どうしてここまで続けられたのかと、率直に聞いた。
金森氏は迷いのない答えをくれた。
「子どもが大切なことを教えてくれる。」
「そして待ってくれている子どもたちがいるから。」
自分の身体がどれだけ辛くとも人を思いやる気持ちを持つ子どもたち。
彼ら彼女らは、それがどんなに短い時間だったとしてもその子にしか生きられない人生を生き抜き、その人生を全うして一生懸命に生きていた、と。
東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科准教授として、取材をさせて頂いたが、話を掘り下げるにつれて見えてきたのは金森氏の子どもへの愛情と尊敬ともいえる想いだった。
すべての子どもには最善の環境で「生きる権利」があり、その命の時間にかかわらず、自分の意思で生きられるということが最優先されるべきなのではないだろうか。
一方で、自分の人生を「生きる権利」を奪われてしまう子どもたちもいる。
親のエゴで。あるいは社会の仕組みの狭間で。
国は平成28年に児童福祉法を改正し、「社会的養育ビジョン」の中で明確に「家庭養育優先原則を徹底し、子どもの最善の利益を実現していく」と述べている。
「家庭養育優先」ということは、実親が育てられない場合、次に家庭的養育といわれる、特別養子縁組や、里親を優先し、施設養育は最終手段であると位置付けるものだ。
施設養育を否定するわけではなく、子どもの最善の利益を考え、家庭的養育が必要な子どもたちには「愛情あふれる家庭」が与えられる事を願わずにはいられない。
最近、熊本慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」に興味を持ち調べていく中で、「家庭」そして「社会」の歪みが「こうのとりのゆりかご」設立からの10年間で預けられた130人の子どもたちの背景に見え隠れしていると感じていた。
金森氏の取材を終え、記事の構成を考えているうちに「家庭」の理想のカタチについて思考を広げるようになった。
当然答えは見つからないのだが、一つに、お互いを尊重しあい、助け合える、何より普段と違うことに気づくことのできる距離感が必要なのではないかと思う。
&family..
千田真司
参考書籍:子どもが病気になる前に知っておきたいこと-病児・病後児保育の考え方-
高野 陽・金森三枝著